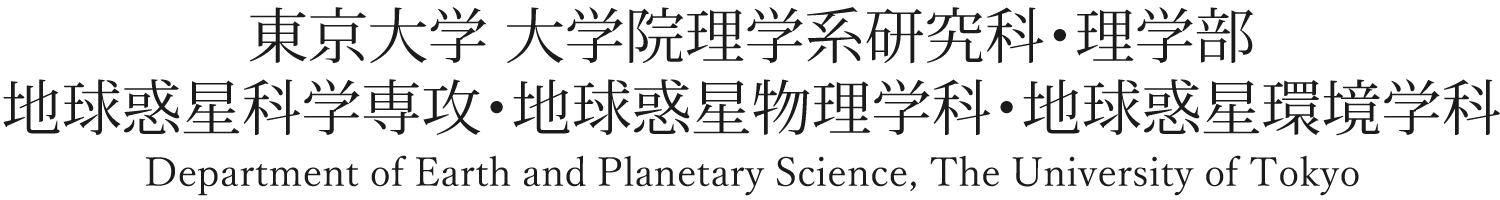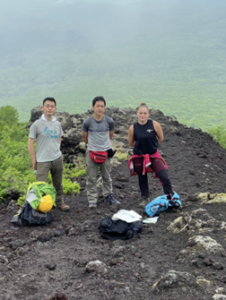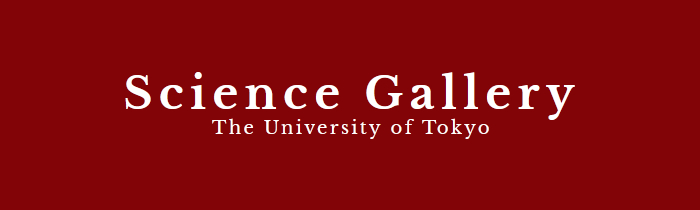【学生の声2024】火星の天気を知りたい!
2024年度「学生の声」
阿隅 杏珠(地球惑星科学専攻 博士1年)
私は火星大気の研究をしています。そのせいか、最近「火星人」と呼ばれることが増えてきました。あまりに安直だ、と無視する手もあっただろうに、むしろ内心うっすら喜んでいる自分に気が付き我ながら呆れるばかりです。
恐らく、これを読んでくださっている方の多くは大学院入試や大学院での生活に関する情報をお集めのことと思います。本稿を書くにあたり、私自身も、先人の書かれた「学生の声」をいくつか拝読しました。中でも、こちらhttps://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/focus20220801/は、高校生から大学院生までを対象とした情報がほぼすべて網羅されており、大変参考になります。さて、地球惑星科学専攻のバイブルともいえる情報源も紹介したことですし、ここらで筆を置いてもいい気がするのですが・・・どうやら火星人にも良心があるようです。せっかく「学生の声」執筆をお声がけ頂いたので、私にしか書けないことを、すなわち、火星大気の研究を始めるに至った経緯を記していこうと思います。
小学生くらいの頃から宇宙に漠然とした興味を持っていました。「宇宙への漠然とした興味」を言語化するのは少し難しいのですが、ざっくりいうと直接肌で感じ取ることのできない地球の外側の領域に魅力を感じていたようです。これは中高を経ても変わらず、地球惑星物理学科(以降、地物)に進学後も、宇宙惑星に関わる研究が出来たら嬉しいと思っていました。一方、地物の授業で面白いと感じたのは地球流体力学や気象学でした。身近な大気現象が数式である程度クリアに説明できるという点に惹かれました。学部生の頃は陸上部で長距離走に打ち込んでおり、日常的に天気への関心が高かったことも関係していたかもしれません。というのも、試合の一週間前から頻繁に天気予報を確認し、気象条件に合わせた調整方法を考えたり、思い通りの走りが出来なかったときの言い訳を考えたりしていたからです。
このような背景から、4年前期の論文講読では、大気物理学を選択し、地球大気大循環に関する理論的な論文を読みました。専門用語がまったくわからなかったため、いくつもの教科書を行き来しながら、亀もびっくりのスピードで読み進めることになりました。一方で、実際に手を動かして数式を追っていく過程には、思いのほか楽しさを感じることができました。この演習を終えた頃には、もともと持っていた宇宙や惑星への関心とも重なって、「惑星大気の研究は面白そうだ」と、研究の方向性が次第に定まってきたのを覚えています。ちょうどその頃、この演習を担当されていた現在の指導教員の佐藤薫先生から、「例えば火星は地軸の傾きや自転周期が地球とほぼ同じため、地球と同じ手法で研究ができる可能性がある」と教えていただいたことも、大きな後押しとなりました。
院試を乗り越え、前述の佐藤薫研究室への配属が決まりました。地球以外の惑星を研究するのは私が初めてだったこともあり、当時は若干の心細さを感じていました。しかし、地物演習でお世話になったある先生の、「境界領域の研究は、両方の領域に興味を持ってもらいやすいが、まずは一つの分野で専門性を身につけることが大切」という話を思い出し、まずは所属研究室で、地球を対象に発展してきた気象学をしっかりと身に着けようと思うようになりました。
以上が、火星大気の研究を始めるに至った経緯です。
“隣の王道気象学の研究室では、同級生がなぜか火星大気の研究をしています(本当に何故だろう……?)”
(冒頭に紹介したバイブルの5節:大学院入試(・研究室選び)の最終段落からの引用)
勝手ながら「学生の声」という場をお借りして、この問いに対するレスポンスとさせていただきます。
私の研究内容を詳しく知りたいという物好きな方はこちらhttps://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/10683/をご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。皆さまがご自身にとって納得のいく進路を選ばれますよう、心よりお祈り申し上げます。
阿隅 杏珠(地球惑星科学専攻 佐藤研 博士1年)
[2025.03公開/2024年度「学生の声」]