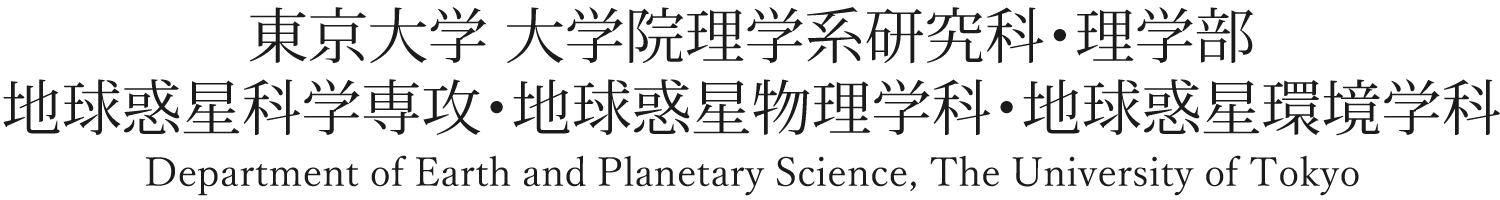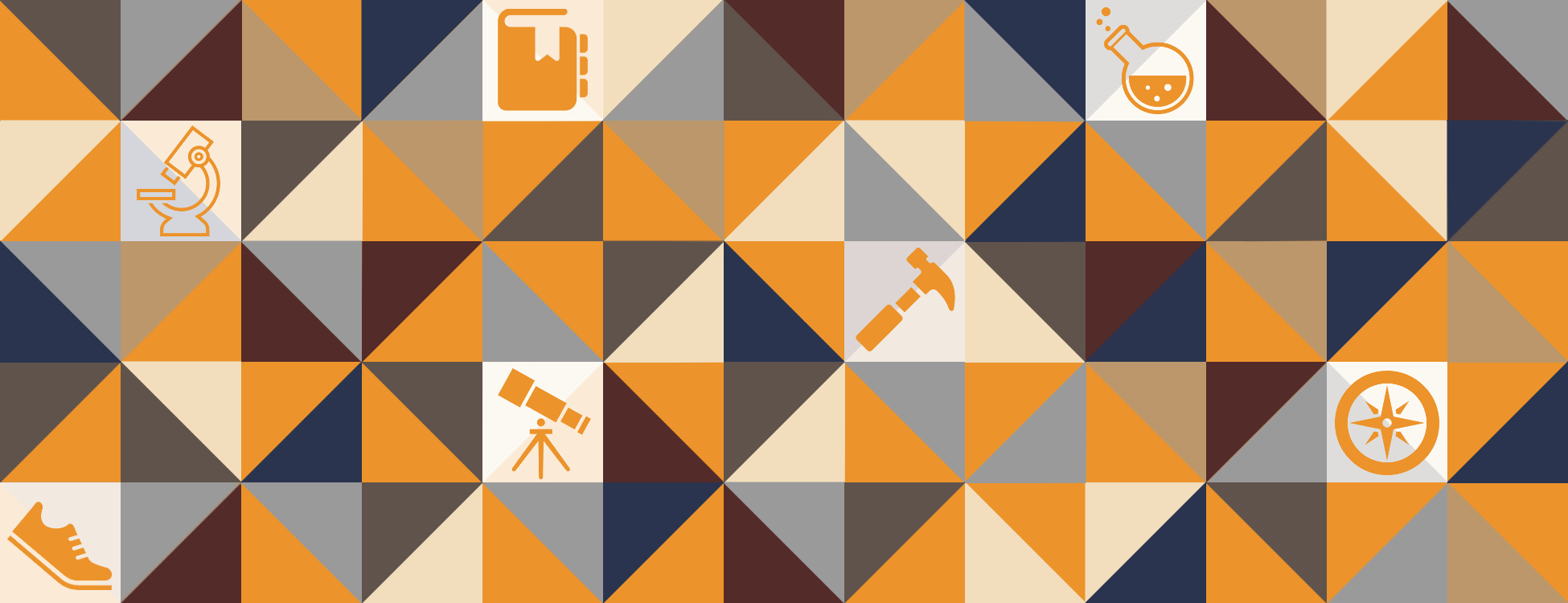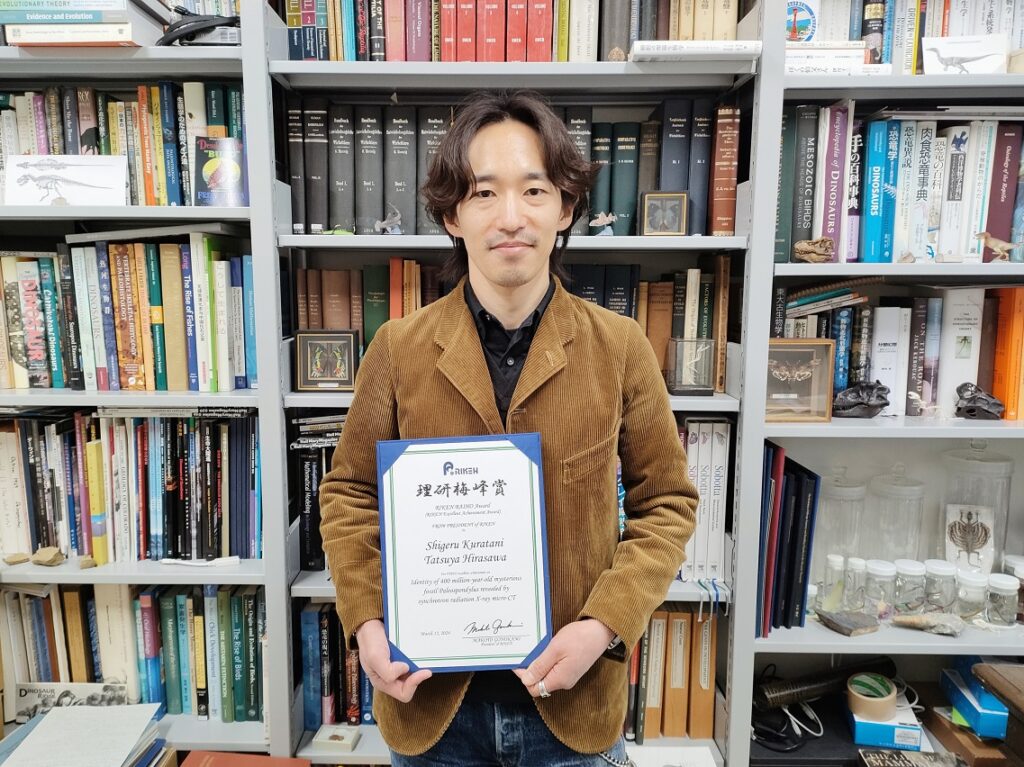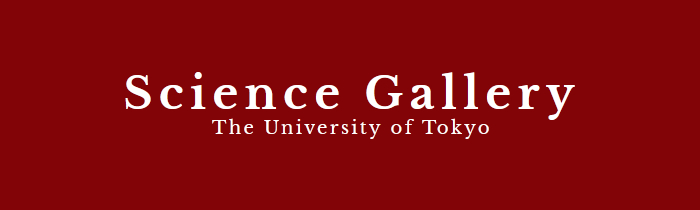地球惑星環境学では、地球や惑星とその環境の進化・変動、生命の誕生・進化・絶滅、そしてそれらの相互関係を実証的に解明していきます。
自然科学的立場にたって、過去から現在にいたる地球や惑星の環境をさまざまな時間・空間スケールでとらえ、その変動や変化を支配する物理・化学・生物の法則を理解することは、現在や将来の地球環境を考える上でも重要です。
地球惑星環境学科では、こうした思考を身につけるため、地球や惑星を構成する物質、過去の地球環境変動を記録した地層、生物進化を物語る化石などの観察や分析、あるいは現在の地球環境の観測や生態系の観察などを通じた、自然現象の実証的な理解と、それに必要な基礎学力と論理的思考の育成に重点をおいた教育 を行います。
学生のみなさんへ
これからの進路を選択しようとしているみなさん、地球惑星環境学科でともに学びませんか。
太陽系の惑星の一つである地球の環境は、さまざまな物理現象、化学現象、生命活動が互いに関連しあう複雑なシステムです。
私たちの学科では、この複雑なシステムの過去を学び、現在を知り、未来を予測するため、これらのすべての基礎と現象の相互作用の理解をめざしています。
――今、なぜ地球惑星環境科学なのか
21世紀を迎えたいま、人類は地球環境の危機に直面しています。私たちは自らの知恵と力によってその危機を解決できるか、その真価が問われています。
しかし、これまでの地球環境問題への取り組みは、個別の問題に対する対処療法がほとんどで、地球と生命の複雑な相互作用を十分に理解したものであるようには思えません。現在や将来の地球環境を考えるためには、地球を大気-海洋-固体-生命の織りなすひとつのシステムとしてとらえ、さまざまな時間・空間スケールでの挙動とその変動メカニズムを理解することが重要です。
地球の歴史において実際に生じたさまざまな地球環境変動の理解は、現在の地球の理解につながり、さらには未来を考える上での重要なヒントを与えてくれるはずです。
カリキュラム
※最新情報は必ずUTAS、ITC-LMS、学科事務室からの通知、講義内でのお知らせなどから確認してください。
詳細はこちら
教養学部Aセメスター(第2学年)
- 選択必修科目(6科目以上/計11単位以上)
-
地球環境学、地球システム進化学、地球惑星物質科学、固体地球惑星科学概論、層序地質学、自然地理学、地球惑星環境学基礎演習I
- 選択科目(8単位以上)
-
物理数学I、物理実験学、天文地学概論、地球惑星物理学概論、地域論、人文地理学、化学熱力学I、量子化学I、無機化学I、分析化学I(総論)、有機化学I、生物化学概論I、人類生物学、進化生物学など
駒場生のための科目選択の手引き・要求科目と要望科目
※最新情報は必ずUTAS、ITC-LMS、学科事務室からの通知、講義内でのお知らせなどから確認してください。
要求科目
文科全類に対して以下の(1)~(3)を履修のこと
(1) (i)か(ii)を履修すること
(i) 基礎科目(数理科学)「数理科学基礎、微分積分学、線形代数学」(計8単位)
(ii) 総合科目F「数理科学概論 I(文科生)、数理科学概論 II(文科生)」(計4単位)
または、総合科目F「数理科学概論 I(文科生)」、基礎科目(社会科学)「数学 II(文科生)」(計4単位)
(2) (i)か(ii)を履修すること
(i) 基礎科目(物質科学)「力学、電磁気学、熱力学または化学熱力学、構造化学、物性化学」の5科目の中から4科目(計8単位)
(ii) 基礎科目(物質科学)「力学、電磁気学」、総合科目E「物質化学(文科生)、物理科学 I(文科生)、地球惑星環境学入門」の5科目の中から2科目(計4単位)
(3) (i)か(ii)を履修すること
(i) 基礎科目(生命科学)「生命科学、生命科学 I、生命科学 II」の3科目の中から1科目(2単位または1単位)
(ii) 総合科目E「現代生命科学 I(文科生、理一生)、現代生命科学 II(文科生、理一生)、微生物の科学、進化学」の4科目の中から1科目(2単位または1単位)
要望科目
総合科目D 「地球環境論、環境物質科学、生態学、社会環境論」
総合科目E 「惑星地球科学 I(理科生)、惑星地球科学 II(理科生)、宇宙科学 I、宇宙科学 II、地球惑星環境学入門、地球惑星物理学入門、細胞生命科学、動物科学、植物科学」
進学に関して疑問・質問のある方は下記までお気軽にご連絡ください。
連絡先
● 学部生の新型コロナ対応に関する相談は、
chikyu-kyomu-wg[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp
[at]を@にしてお送りください。
● その他一般的な相談は、
東京大学 理学部 地球惑星環境学科
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 <理学部1号館>
2021年度 教務担当 後藤 和久
居室:理1号館中央棟室544室
Eメール:goto50[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp
TEL:03-5841-4563
● 進学相談・進学振り分けに関する相談も随時受け付けています。お気軽にご相談ください。
全般 soudan-chikyu[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp