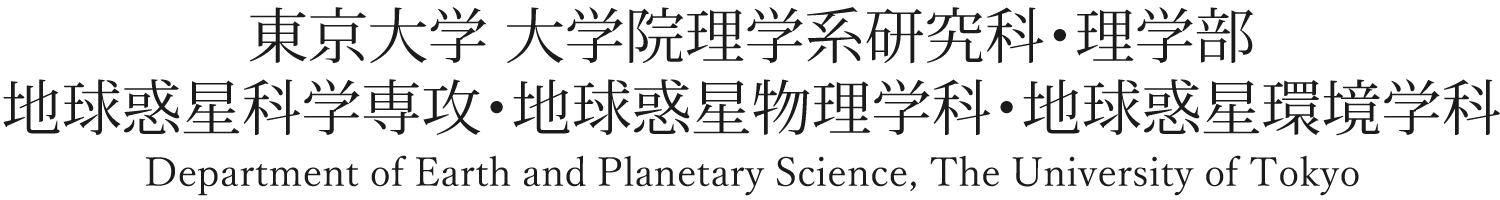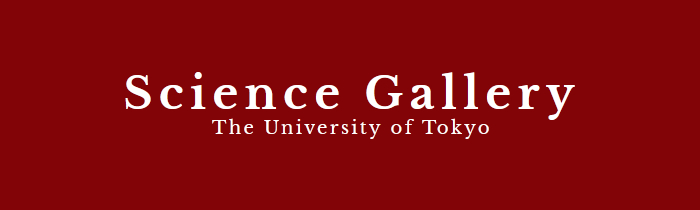糸魚川―静岡構造線の深部から水素依存型の地下生命圏を発見 -プレート境界の水素で探る水・岩石・微生物生態系の相互作用-
プレスリリース
高橋 嘉夫(地球惑星科学専攻 教授)
発表概要
国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸)海洋機能利用部門 生物地球化学センターの高野 淑識 センター長と国立大学法人東京大学(総長 藤井 輝夫)大学院理学系研究科地球惑星科学専攻の西村 大樹 研究生(当時:現在、理化学研究所)および同専攻の高橋 嘉夫 教授、国立大学法人信州大学(学長 中村 宗一郎)理学部の浦井 暖史 助教は、国立大学法人東京大学 大気海洋研究所の横山 祐典 教授らと共同で、長野県諏訪盆地から地下水試料を取得し、地球化学及び微生物学的な分析から、地下微生物生態系の組成と分布、そして地下10 – 1,000 mまでに拡がる地下深部の物質循環を明らかにしました。
諏訪盆地は、北米プレートとユーラシアプレートの境界として知られる糸魚川–静岡構造線上に位置し、多数の温泉が分布することで知られます。我々はこれまで諏訪湖を対象とした研究を展開し、湖底から湧出するメタンが深部の微生物起源であること、そのメタンが諏訪湖内の生態系にとっての重要な炭素源であることなどを示してきました(2022年 6月 15日既報)。この結果は、諏訪盆地の地下深部にメタン生成、あるいはメタン酸化によって支えられた微生物生態系が存在することを強く示唆しています。しかし、地下に分布する微生物の群集組成の多様性、それらを制約する物質循環のメカニズムについてはほとんど未解明でした。
そこで本研究では諏訪盆地の地下水・温泉水を対象に微生物相の網羅的な解析を行い、有機物に富んだ堆積層にはメタンを酸化するバクテリア、熱源を伴う深部の基盤岩層(最大深度〜1,000 m)の温泉水には、水素を酸化してエネルギー獲得を行う水素資化性のバクテリア・アーキアが優占することを明らかにしました。また、水循環を規格化する化学トレーサーとして、放射性炭素同位体分析を含む溶存成分の精密な化学分析を行い、諏訪盆地における天水(てんすい)と地下水の時空間的な流動プロセスを明らかにしました。本成果は、プレート境界での断層活動に伴う地下環境の水素給源と微生物生態との相互作用の理解に大きく貢献するものと期待されます。
本研究は、海洋研究開発機構と信州大学で締結している共同研究の成果の一部です。本成果は、日本地球惑星科学連合(JpGU)が発行する学術誌「Progress in Earth and Planetary Science」に10月1日付け(日本時間)で掲載されました。

詳細については、以下をご参照ください。